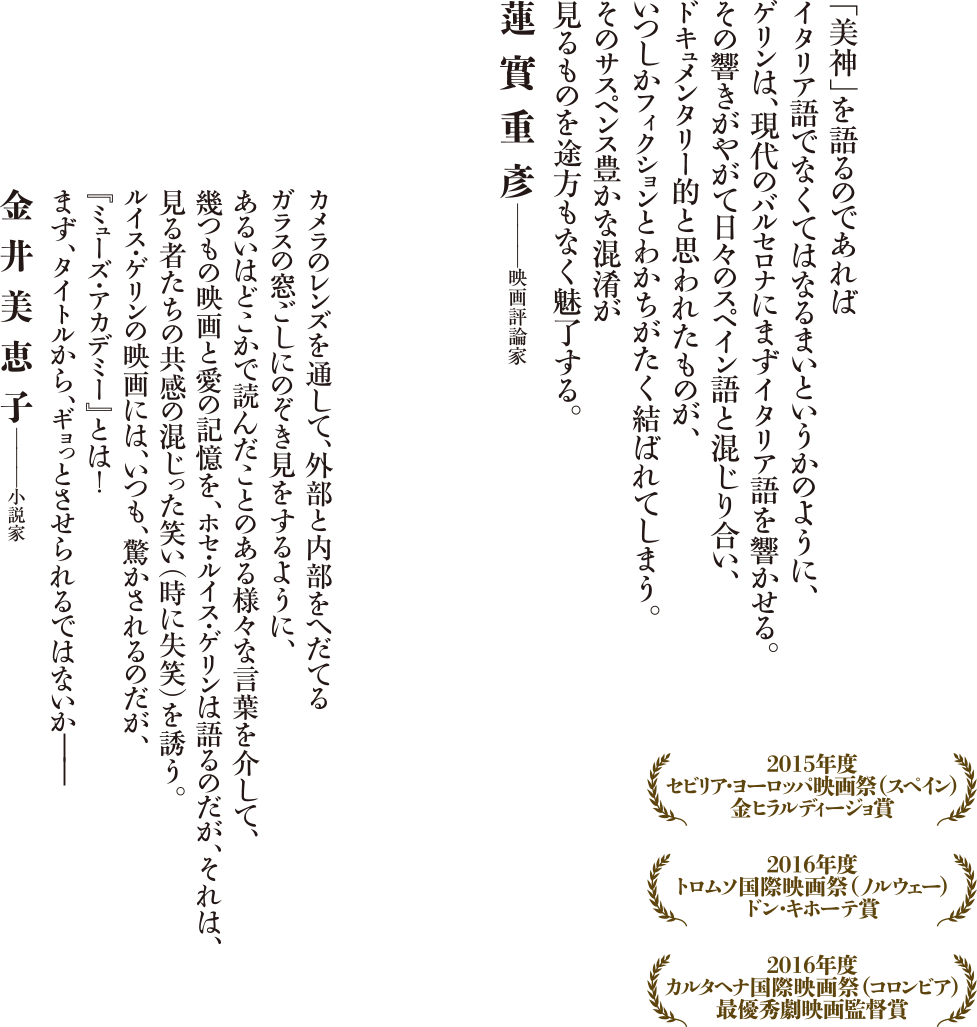

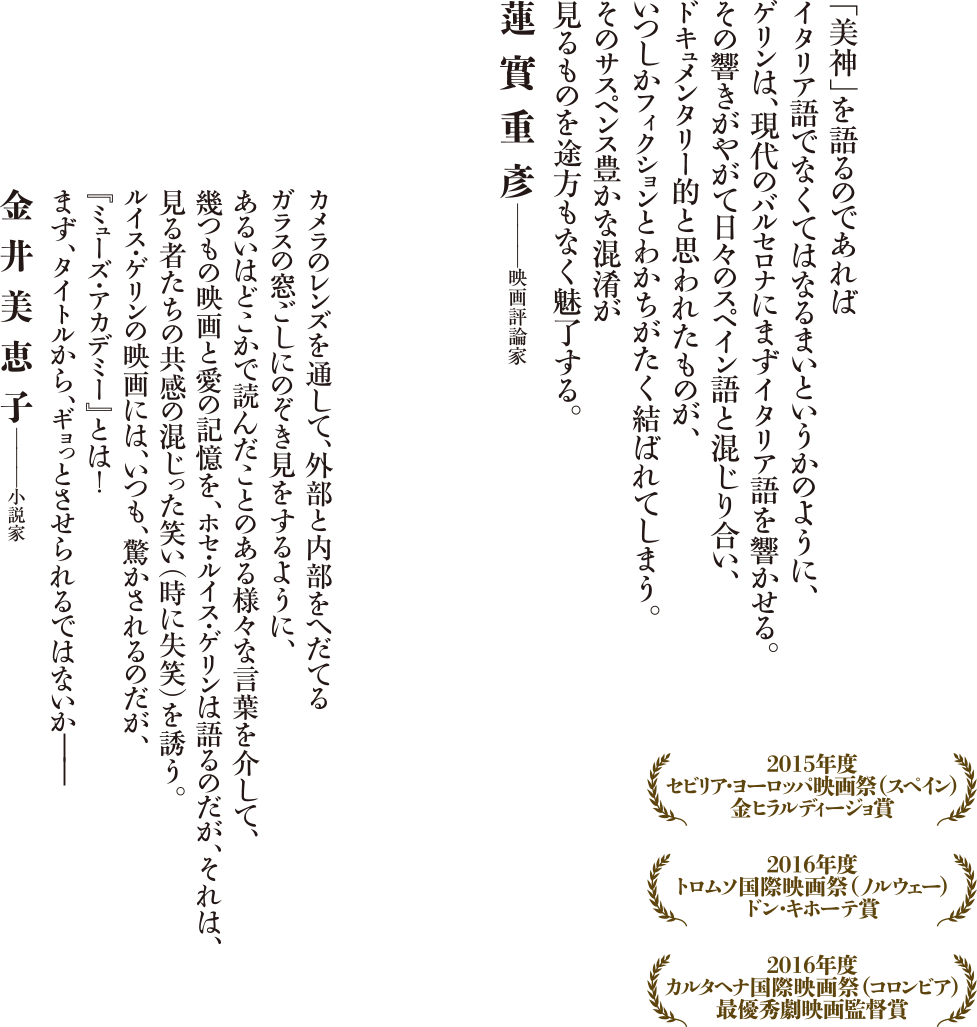

ゴダールにとってのアンナ・カリーナ、小津安二郎にとっての原節子、ウォーホルにとってのイーディ、
そしてダンテが熱烈に愛したベアトリーチェ。古より、多くの優れた芸術の裏には、
いつもその創作欲を奮い立たせる輝かしいミューズ(女神)の存在があった。
バルセロナ大学の教室で、イタリア人のピント教授は、現代のミューズ像を探るべく「ミューズ・アカデミー」を開講する。
それは、詩を通じて世界を再生させる画期的な授業だった。だが高尚な文学や芸術を語る場であったはずの教室で、
教師と生徒の果てない議論は、予期せぬ場所へと向かっていく。一方、教授の妻は「恋愛は文学が捏造したもの」だと言い、
夫のミューズ像を強く否定する。映画にはどこかで聞いたことがあるような痴話げんかや嫉妬の言葉があふれ、
やがて私たちは、教授と教え子たちの関係が変わる瞬間を目撃することになる。
果たして「ミューズ・アカデミー」の行き着く先は、文学の新しい未来か?
それとも彼ら自身の恋愛物語か?言葉とまなざしが交錯する教室で、美と愛の講義が始まる。
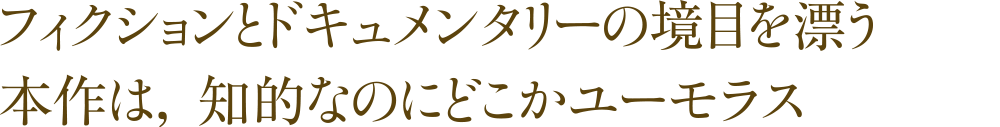
『シルビアのいる街で』が日本でも大きな話題を呼んだホセ・ルイス・ゲリンは、
映画のありかたそのものを問う斬新な作品で、いつも私たちを驚かせてくれる.新作『ミューズ・アカデミー』でゲリンが試みるのは,
実際の大学教室でくりひろげられる授業風景と、そこから派生する彼らの私生活のドラマとを見事に交差させること。
ゲリンは本作をフィクションだと言う。だがカメラが捉えたのは、ドキュメントかと思わせるほどリアルな人間関係、
監督は、「これまでつくったなかでもっとも力強い映画で、自分でつくった作品に驚かされた」と語る。
ピント教授と女たちの白熱する議論は、知的なのにとんでもなくユーモラスで、またときにエロティックな展開さえ生み出す。
スペイン語とイタリア語、カタルーニャ語が入り乱れる映画には、ギリシャ神話の恋人たちから実在の詩人に大きな影響を与えた女性たちまで、
数多くのミューズたちが登場。現代のドラマとともに、ヨーロッパ古典文学のなかのミューズ像についても思いをはせる、
見たことのない斬新なフィクション・ドキュメンタリー!






















